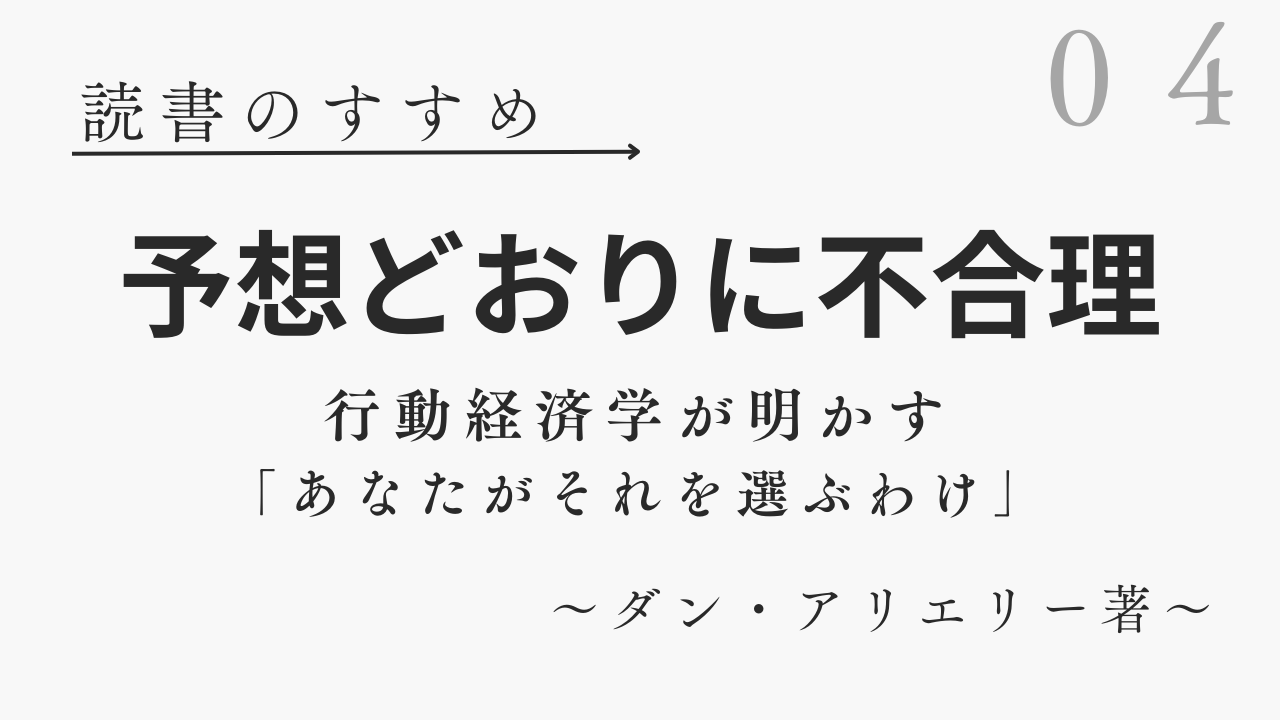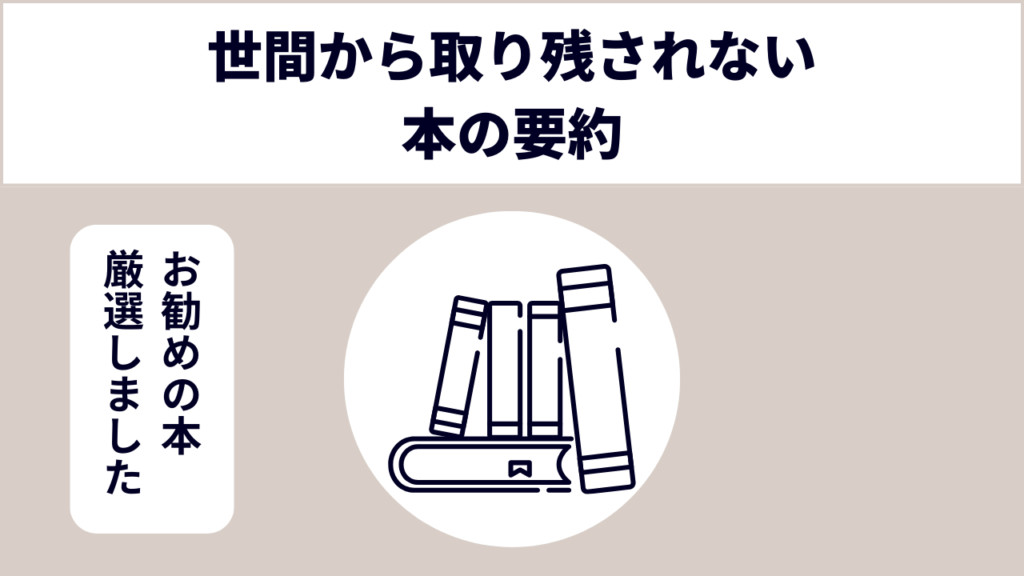この記事は、「予想どおりに不合理 行動経済学が明かす『あなたがそれを選ぶわけ』」(ダン・アリエリー著 熊谷淳子訳)(2013年、早川書房)の要約です。
行動経済学の入門書として必読の一冊です。ニューヨークタイムズのベストセラーリストに含まれています。
ダン・アリエリー(1967-)
・行動経済学研究の第一人者
・イスラエル系アメリカ人
・デューク大学の心理学および行動経済学のジェームズ・B・デューク記念教授
それでは章ごとにポイントをかいつまんでいきます。
はじめに
まずプロローグとして、筆者が行動経済学の研究に足を踏み入れたきっかけが書かれています。
筆者は大火傷の治療の経験があり、その際に看護師が良かれと思って行っているケアが患者に余計な苦痛を与えていることに気がつきました。そこから、「経験を積んでもそこから学ぶことなく失敗を繰り返してしまう状況」について研究しようと決めたそうです。
ここで経済学と行動経済学の違いについても触れられています。それは、経済学では「人間はいつも合理的である。」という立場である一方で、行動経済学は「人間は合理性を書いている。その上、人間の不合理な行動は規則性があり予想できる。」という立場です。
それでは次章からいよいよ、行動経済学の研究の成果をのぞいていきましょう。
1章 相対性の真相
1章では、人間は「ものごとを絶対的な基準で決めることはまずない」ということが述べられています。つまり、人間は「他のものとの相対的な優劣に着目してそこからものの価値を判断している」ということです。
たとえば、
エコノミスト誌の購読案内では、「ウェブ版$59」「印刷版$125」「印刷版+ウェブ版$125」とすることで、本来ウェブ版のみしかいらない人も印刷版+ウェブ版を買うように誘導されている
(「印刷版」と「印刷版+ウェブ版」を同じ値段にし、相対的に「印刷版+ウェブ版」がお得に感じる)
大半の人は自分の求めているものを分からずにいて、状況と絡めて自分が求めているものを知ります。前の例では、印刷版より印刷版+ウェブ版が明らかに良く見えるので、あまり悩まずに選択できる(させられている)のです。
さらに人間は、「比べやすいものだけを一生懸命に比べて、比べにくいことは無視する」という習性があり、それを元にした「おとり効果」が有効に使われていることがあります。
たとえば、
ヨーロッパ旅行を計画した際、航空運賃、ホテルの宿泊、観光、朝食無料サービス込みのパッケージツアーでローマとパリを提示されると選びにくい。しかし、そこに朝食無料サービスのないローマのパッケージツアー(ローマ’)が提示されると、ローマ、ローマ’、パリの中での選択となる。するとローマ’のおかげでローマが引き立ち、ローマが選ばれやすくなる
このように相対性を以て判断することは人生における決断を助けますが、一方で妬みや僻みを生みます。特に給料を相対性で判断すると如実です。
例として、
CEOの給料を公開することで幹部の給与上昇を止めようとした結果、CEO同士が給料を比べ始め余計に上昇した
これを突き詰めた結果、金持ちが大金持ちに嫉妬する時代となりました。人は持てば持つほど欲しくなる生き物であり、そうならないためには相対性の連鎖を絶つしかないと書かれています。
2章 需要と供給の誤謬
2章は黒真珠の話から始まります。
もともとタヒチの黒真珠は販路がなく需要もほとんどなかったが、いきなり法外な値段をつけニューヨーク五番街のショーウィンドウにダイヤモンドやエメラルドと並べて飾り、大々的に広告することで高級品にしました。
人々に価格を刷り込むことに成功したのです。
私たちが何かの商品を買おうとすると、その時の価格が刷り込まれます(その価格を学術用語でアンカーと言います)。すると、その後に他の買い物をする際にもその価格を参照するようになります。
たとえば
住宅価格については、自分が住んでいる土地の住宅価値相場に慣れてしまい、他の土地に引っ越した後もその価格を元に考えてしまう
このように、最初の決断によって長期の習慣が変わるのです。
たとえば、
・最初にスターバックスにコーヒーを何の気なしに飲みにいくと、その後も繰り返し行くようになることがあります。前にその決断をしたのだから、それが正しいお金の使い道だと思い込む
・トムソーヤの冒険では、ペンキ塗りの雑用を楽しそうにやっている様子を見せることで面白いものだと思わせ、逆にペンキ塗りにお金を取るようになる
このように、最初の決断はその後何年にもわたる決断に影響を与えることがあるので慎重にする必要があります。そして、自分の人生におけるアンカーを再検討する必要があります。
また、市場価格は需要と供給で決まりますが、需要は簡単に操作されうるのです。アンカリング操作では市場価格が先に決まっています。ものの値段が上昇してもしばらくは需要が落ちるかもしれないが、しばらくすると新しい価格がアンカリングされます。
自由市場は、私たちが欲しい品物のの価値を把握しているという過程に支えられていますが、実際には価格は得られる満足や効用を正しく反映しているとは限りません。そのため、特に社会に不可欠なものには自由市場の制限が必要かもしれないということを考慮する必要があります。
3章 ゼロコストのコスト
3章では、自分が求めているものでなくても、無料になると飛びついてしまう、ということが書かれています。
たとえば、
15¢のリンツのトリュフと1¢のキスチョコでは、(より割引されている)リンツのチョコを選択する人が多いですが、(どちらもそこから1¢割引きしただけの)14¢のリンツのトリュフと無料のキスチョコではキスチョコを選ぶ人が増える
無料のものを選べば目に見えて何かを失う心配がないが、無料でないものを選ぶと誤った選択をしたかもしれないという危険性があるので、無料を選ぶのです。
その結果、無料で付いてくるもののせいでいらないものを買ってしまうことがあります。配送料の無料やカロリーゼロにも同様のことが言えます。
逆に言えば、無料を利用することで、売上を伸ばしたり社会政策を推進したりすることもできるのです。
4章 社会規範のコスト
4章は、世界は市場規範と社会規範という2つの規範によってできているというお話です。
- 社会規範には、友達同士の頼み事のようなものが含まれ、すぐにお返しをする必要はない
- 市場規範は、シビアであり、対等な利益や迅速な支払いが求められる
この社会規範と市場規範を混同すると厄介なことが生じます。
元々社会規範の中で活動をしていたとしても、その活動にお金が提示されると人は市場規範の中で働くようになります。そして、支払われる額が見合っていない場合には、社会規範の内であったとき(タダ働き)よりも熱心に働かなくなるのです。
さらに困ったことに、いったん市場規範が入り込むとなかなか社会規範は戻れません。
人をやる気にさせるのはお金に頼るのが最も高くつきます。
そんな中で顧客や社員との間に社会規範を確立しようとする取り組みがあります。社会規範にいかに留まれるかが鍵となります。
5章 無料のクッキーの力
5章では前章の発展として、社会規範と市場規範の需要への影響について述べられています。
以下は、クッキーを「5¢で販売」「無料配布」「クッキーをもらうのに簡単な作業をする」という場合に、人がどれだけクッキーを手に入れようとするか、という実験です。
- クッキーを5¢で販売した時:たくさん買う
- クッキーを無料配布した時;1,2個しかもらわない
- クッキーをもらうのに簡単な作業をさせる場合:上記の中間に落ち着く
このような結果になるのは、「5¢で販売」した場合は市場規範が働き、「無料配布」した場合は社会規範が働くためです。
そして、労力は社会規範と市場規範の間に位置することがわかります。労力を伴う取引が金銭的取引に比べて社会規範を維持できるのです。
現金ではなく労力を投資することは経済効率は悪いですが、そうすることで社会規範にとどまることができ他者の幸福を考慮できるようになる可能性があります。
たとえば、
いわゆるPTA活動は、人をお金で雇う方が楽であるにも関わらず、家族に労力の投資を求めることで社会規範にとどまっている
6章 性的興奮の影響
6章では、性的嗜好、道徳性、安全な性行為への取り組みについて、性的興奮が与える影響を興奮していないときに予測することは不可能だということが述べられています。

この章は、過激な表現が含まれるため、詳細は書籍をご覧ください…笑
誰もがジキルとハイドであり、自分で自分をコントロールできると思っていてもいざハイドになってしまったら自己制御不能となるのです。
そのため、はなから誘惑を避ける方が誘惑に打ち勝つよりも簡単だと書かれています。
前編まとめ
前編は6章までのまとめとなります。いかがでしたでしょうか。
本書の魅力が伝われば幸いです。7章からは後編で要約していきます。
\ 他にも様々な分野の本を要約しています /