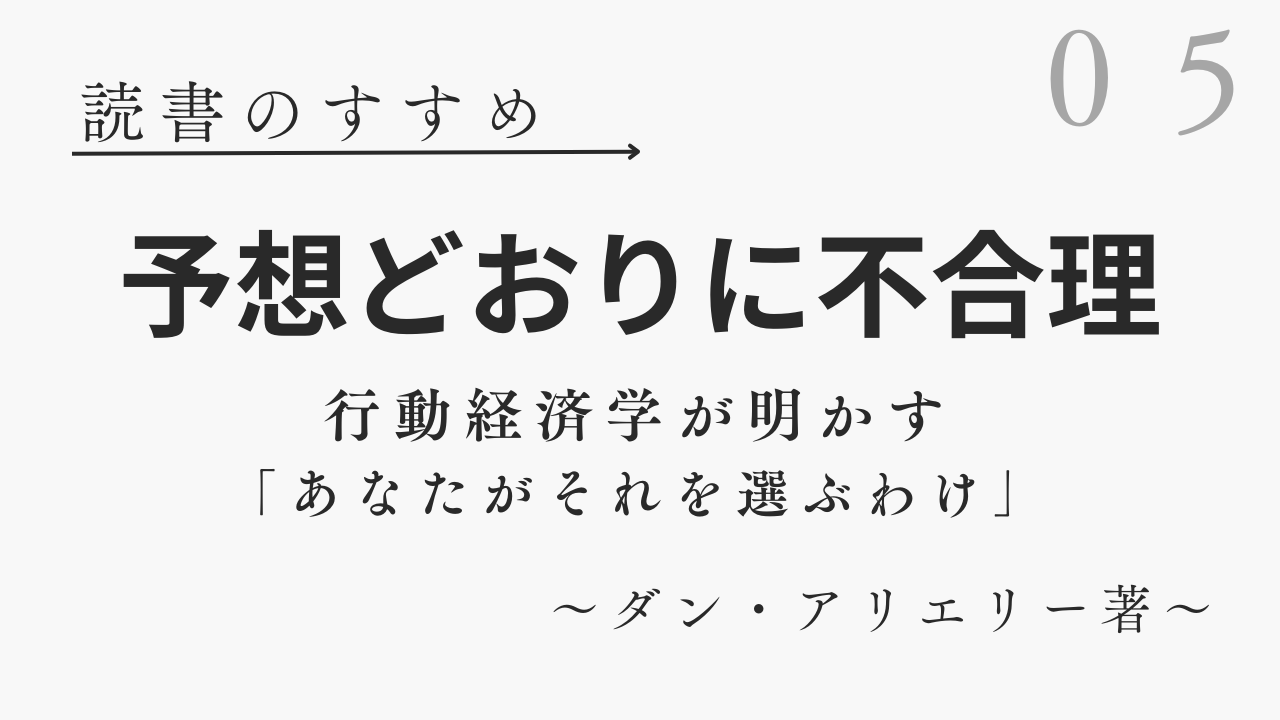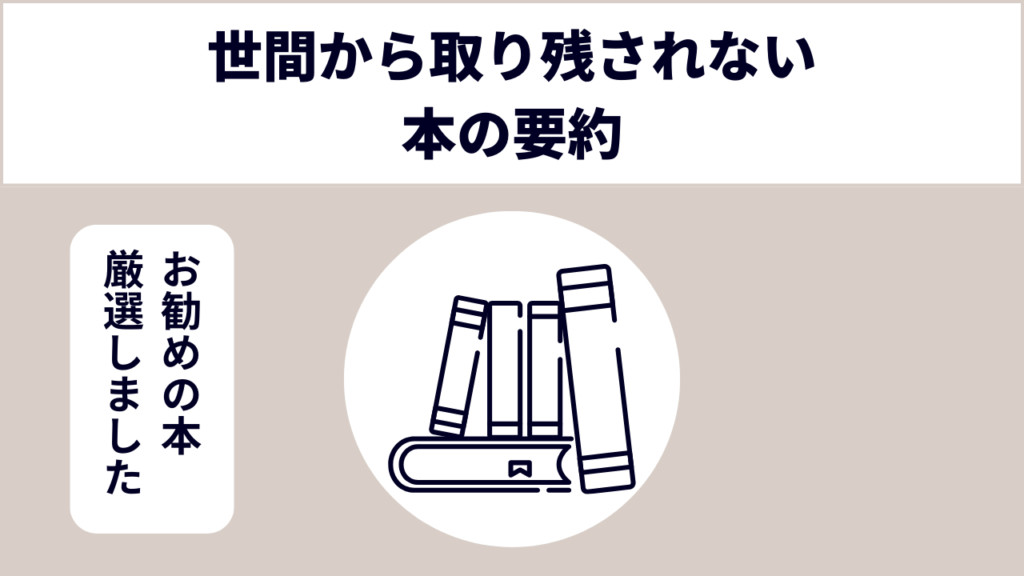行動経済学の入門書である「予想どおりに不合理 行動経済学が明かす『あなたがそれを選ぶわけ』」(ダン・アリエリー著 熊谷淳子訳)(2013年、早川書房)の要約です。
後編の記事です。※前編からご覧いただくことを推奨します。
それでは7章から要約していきます。
7章 先延ばしの問題と自制心
7章は、私たちを常に悩ませている「先延ばし」についてです。
以下は、レポートの締め切りと成績の関係性についての実験です。
「①レポートの締め切りを設定した場合」「②自ら締め切りを設定させた場合」「③締め切りを設定しなかった(学期中ならいつ提出しても良いとした)場合」では、①→②→③の順番に成績がよかった
世の中のほとんど全ての人が先延ばしにしてしまうという問題を抱えています。この結果は、その中で自分の弱点を自覚し、認めている人の方が事前の決意表明で利用できる道具を使いやすく、自力で問題を解決できやすいということを示しています。
自制に役立つ仕組みの利用を検討してみるのも良いでしょう。たとえば、給料から貯金できないなら会社の自動積立制度を利用するという方法もあります。ひとりで規則正しい運動ができないなら友人と一緒に運動する約束をするということもできます。
医療での先延ばし対策についての案についても興味深いアイデアが示されています。
たとえば、検査の予約を取る段階でお金を請求され、実際に検査を受けるとお金を返却されるようにする、というもの
8章 高価な所有意識
8章は、人は何かを手にした途端に愛着を感じる、という内容です。
愛用のものを売る際には失う経験に注目してしまい法外な値段をつけてしまう、といったことも書かれています。

ぶきは逆に自分のものを過小評価して安く売り叩いてしまいがちなので、↑の内容はあまりしっくりきませんでした…汗
何かに打ち込めば打ち込むほど所有意識は強くなります(例えば、自ら手を加えた自宅など)。
さらに所有する気になっただけでも所有意識は生じてしまうようです。
たとえば、
・オークションでは自分が一旦所有者だと感じるとその立場を失わないようについつい予算よりも多く入札してしまう
・商品のお試し期間に所有してしまうとその期間が終了してもやめられない
9章 扉を開けておく
9章は、中国の秦末期の武将・項羽の話から始まります。
項羽は、秦軍を撃退するために黄河を渡った後、渡ってきた船をや鍋を燃やして退路を絶った。勝利か全滅か以外の選択肢をなくすことで士気を上げた。
人は普通、別の選択肢を閉ざすことが耐え難いものです。上記の例で言うと、一部の兵を船の見張りにつけたり食事が係につけたりしてしまうことでしょう。
現代の世の中でも、必要以上の機能がついたPCを買ったり、子供に多くの習いごとをさせたりしてしまうのは、選択肢を減らさないようにするためというのもあります。
人間には、無用な選択肢を追い求めたくなる不合理な衝動があるのです。
10章 予測の効果
10章は、同じ出来事でも状況によって解釈が異なる、というお話です。
たとえば、
・時間ギリギリのゴールが入ったかはどちらのチームを応援しているかで意見が異なる。
・レストランの雰囲気が高級なら、味も高級に感じる。
・詳細な料理の説明は、料理を素晴らしいものと予測させる。
ステレオタイプを抱くと抱いた側だけでなく、ステレオタイプ化された人たちも押し付けられたレッテルに気付けば反応が変わります(心理学ではプライミングと言います)。
先入観や予備知識を取り去ることが不可能でも、誰でもみんな偏っているのだと認めることはできます。
11章 価格の力
11章は、正しいと思って行われてきた手術がプラセボでも同様の効果を認めた、という話から始まります。
過去に行われていた、狭心症に対する内胸動脈結紮術、慢性腹痛に対する癒着剥離術など
プラセボの仕組みは、信念(薬や治療・世話をしてくれる人に対する信頼、確信)と条件付け(慣れによる予測)です。
また、価格は経験を変化させる可能性があります。
たとえば
・価格が高い薬はよく効くように感じる
・一般市販薬も定価で買った方が割引で買うよりも効くように感じる
ここで生まれる疑問は、プラセボで効果が得られるのならその効果を楽しめば良いのではないか、あるいはプラセボは破棄すべき紛い物なのか、ということです。
実際プラセボは、心が体をうまくコントロールすることを体現しているのです。
現実には医師は患者の求めに応じていつもプラセボを出しています。たとえば、多くの風邪はウイルス性なのに患者の安堵のために抗生物質を出す、という例が挙げられています。
医師は科学的な人間であるので、この行為に居心地の悪さを感じています。

「居心地の悪さ」は医師の気持ちをよく表した表現だと感動しました(笑)
ただ、耐性菌の問題から最近ではあまり風邪に対して抗生物質は処方しません。しかし患者さんの要望が強く、「それで気持ちが救われるなら」と処方される場合があるのも事実です。
プラセボ実験の倫理的問題と行わないことで払う犠牲についてのジレンマは常に課題です。
12章 不信の輪
12章は、信用を裏切られると裏切った相手以外にも不信感を募らせるようになる、というお話です。
企業が私たちに持ちかけてくる提案が私たちのためではなく企業のためのものであることを一般の人たちが理解し始めました。その結果、私たちはさらに用心深くなり、誰に対しても不信感を募らせるようになった。
経済学者のお気に入りの主張に「100ドル札が歩道に落ちていることはない」もし落ちていることがあればすでに誰かが拾っている、というのがある
信用と裏切りについて回る問題が共有地の悲劇です。
長期的な観点から個人は共有資源の持続可能性を気にかけています。しかし同時に、短期的に見ると個人は自分の公正な取り分以上に取ることですぐに利益を得ることができます。
「公共財ゲーム」も同様の論理です。
最初は信用していた人も、他人が信用に足らないことがわかると信用できなくなり、そうしてどんどん信用を失う、という悪循環に陥ります。
暗い話が多い中で、迅速な対応をし信用を回復した模範として、ジョンソンエンドジョンソンのタイレノール騒動が挙げられています。企業が透明化し無防備になることで信用を得られます。
多くの企業が広告や提案で嘘をつきますが、見咎められずにすんでいます。しかし、囮広告を繰り返すと張本人だけでなく業界全体の信用が落ち、そして一度落とされた信用を回復するのは難しいのです。
13章 わたしたちの品性について その1
13章は、自分のことを正直だと思っている私たちによる不正についてです。
最初に衝撃の数値が挙げられています。
- 2004年のアメリカの強盗事件の被害額は$5億2500
- 一方で従業員による職場での盗みや詐欺は年間およそ$6000億
- 支払われるべき税金と支払われている税金の差額は$3500億
強盗や泥棒による犯罪学よりも善良な市民による損害額の方が圧倒的に多いのです。
さらに腐敗した経済活動で得られる金額は、家庭を狙う標準的な泥棒など比べ物になりません。
このように、世の中には「強盗を連想させるような不正」と「普段自分が正直者だと思っている人が犯す不正」の2種類の不正があります。
正直ものだと思っている人による不正は、不正ができるような試験を行うと少しの不正をするものの満点を取るようなことはしないのです。
それは、私たちは正直を大切にしており、正直監視モニターは搭載されているが、そのモニターが反応するのは大きな違反行為を働こうとする際のみ、のためです。
外からコントロールして正直を強制してもうまくいく場合といかない場合があります。腐敗を一掃しようとしても、法律の穴を潜り抜けようとします。
実験では、試験前に十戒を思い出させただけで不正が減りました。そして十戒は覚えていない人も多く、道徳基準に思い巡らすだけで十分なようです。
アダム・スミスが示した通り正直が最善の策であり、経済大国であり続けるためには正直な国家を維持することが必要です。
14章 わたしたちの品性について その2
14章では、さらに正直者による不正の話が続きます。
ここでは、たいていの不正行為は現金から一歩置いたところで行われている、ということが示されています。現金そのものでは不正行為はしないのです。
今、現金を使う時代は終わりを迎えようとしています。
そのため、現金から一歩離れると人はとんでもない不正をすることを認識しなければなりません。
15章 ビールと無料ランチ
15章では、独自性の欲求についてと、これまでのまとめが為されています。
独自性の欲求の例として
レストランでテーブルで順番に注文を取ると、テーブルを囲んでいる人たちの最終的な注文に影響する
最後にまとめとして筆者からのメッセージが続きます。
- 私たちはみんな、自分が何の力で動かされているかわからないゲームの駒である
- 私たちはたいてい自分で進路や決断をコントロールしていると思っているが、これは願望に過ぎない
- 感情、相対性、社会規範などは私たちの行動に多大な影響を及ぼしているのに、私たちはそれらを過小評価している
- 不合理が当たり前のことであっても、決断を見直す努力や科学技術を使ってこの弱点を克服することもできる
まとめ
「予想どおりに不合理 行動経済学が明かす『あなたがそれを選ぶわけ』」を要約してきました。最後までご覧いただき、ありがとうございました。
ここでは、本の中で(私の主観で)特に印象に残った点をまとめたに過ぎません。実際に書籍を読むことで新たな発見があると思います。
皆様が、本書に興味を持っていただけていれば幸いです。
\ 他にも様々な分野の本を要約しています /