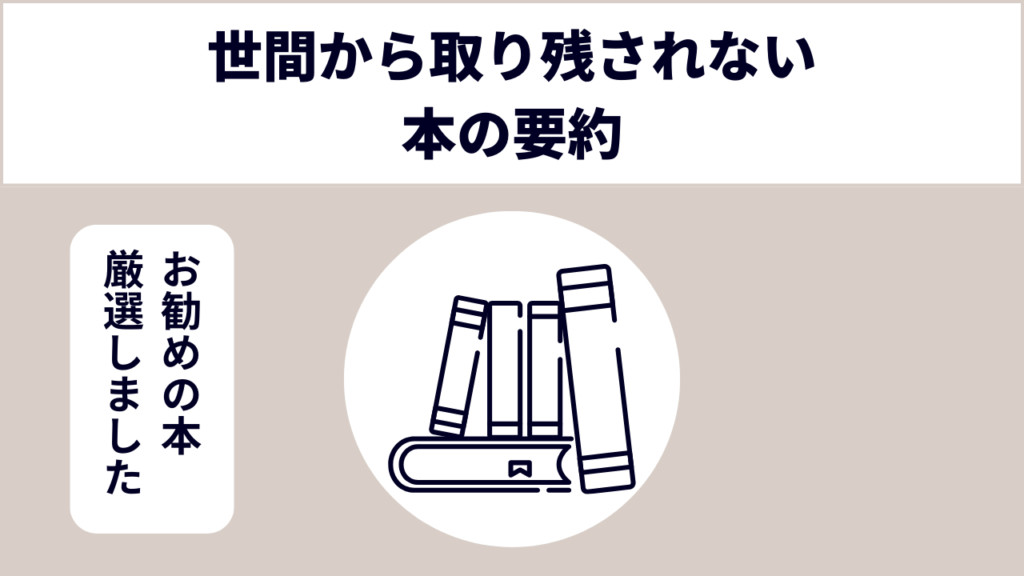今回は、茂木誠先生の著書「経済は世界史から学べ!」(2013, ダイアモンド社)を要約していきます。
第1章 お金(1) 円・ドル・ユーロの成り立ち
No.1 なぜ、1万円札には「1万円の価値」があるのか
お金を支えるのは発行者の信用
政府が民間の金融業社による金銀預かり証を真似して紙幣ができました。
しかし政府は無駄遣いし紙幣を乱発してインフレになります。
そこで中央銀行がお金を管理し、国債を引き受けるようになりました。
イギリスでは、国王ウィリアム3世により設立を許可されたイングランド銀行が、国債を引き受け紙幣発行権を得ました。
※ウィリアム3世(1650-1702)(オランダ総督)
イギリス王女との婚姻関係から名誉革命に協力してイギリス王として即位。
フランスとの植民地戦争で財政難に陥り、イングランド銀行の設立を許可。
No.2 ドルの歴史ー巨大財閥が「ドル」を動かす
かつてアメリカには、「2つのドル紙幣」が存在していた
ドルは連邦準備制度理事会(FRB)が発行しています。
元々各州が独自通貨を発行していましたが、初代財務長官ハミルトンが合衆国銀行を設立し統一通貨ドルを発行しました。
リンカーン大統領は、南北戦争の戦費調達のため政府紙幣を発行しますが、勝利後に暗殺されます。
力を持った新興財閥は政府紙幣に反対し金本位制の採用を求めました(特にモルガン銀行は事実上の中央銀行となりました)。
1907年の恐慌後に金融資本の合意とウィルソン大統領の認可を得てFRBが発足しました。
出資者はすべて民間の金融機関です。
1960年代にベトナム戦争と福祉の財源としてケネディ大統領が財務省に発行させた合衆国紙幣は、ケネディ暗殺により回収されました。
No.3 円の成立① 「金」をめぐる幕末の通貨戦争とは?
江戸幕府の貨幣制度を悪用した外国商人
江戸時代は金銀銅の通貨が流通していましたが、元禄時代に金銀が枯渇し幕府は財政難になりました。
勘定奉行(財務大臣)の荻原重秀は、貨幣改鋳で金銀の純度を下げ本位通貨から信用通貨に転換しました。
荻原失脚後も思想は受け継がれ、田沼意次は金銀交換レートを設定しました。
ところが欧米では本位通貨制が継続しており、金銀交換比率の違いから日本の金銀が流出しました。
※荻原重秀(1658-1713)(江戸時代、勘定奉行)
5代将軍徳川綱吉に抜擢され、財政再建のため再検地(国税調査)と貨幣改鋳(金融緩和)を実施。
元禄バブルを現出したが、悪性インフレを招いた。
No.4 円の成立② 大蔵省と日銀の戦い
通貨発行権をめぐって、「官」と「民」は戦い続けてきた
明治維新後の政府紙幣(太政官札)は、新政府の信用が低く流通しませんでした。
大蔵次官の大隈重信は153の国立銀行を認可し、銀貨「円」の発行権を与えました。第一国立銀行の出資者は両替商の三井組でした。
西南戦争によるインフレを克服するため、大蔵卿の松方正義は中央銀行として日本銀行を設立し、銀本位制に基づく日本銀行券を発行しました。
出資者は半分は政府、半分は三菱・三井・安田財閥でした。
昭和恐慌下、高橋是清蔵相は積極財政を進めて不況を脱した後、緊縮財政に転じようとして暗殺されました(二・二六事件)。
日銀法で日銀は大蔵省の一部局となり、歯止めない通貨発行により戦争は拡大しました。
敗戦後、GHQと協力した日銀は新円を発行して戦後インフレを克服しました。
ただ大蔵省が事実上日銀を支配していました(旧日銀法)。
ニクソンショック、円買いドル売りの協調介入などを経て(No.11,12参照)、日本でも日銀の独立性が叫ばれるようになりました。
1997年に日銀は大蔵省から独立し(日銀法改正)、通貨の安定と中央銀行の独立を盾に政府の金融政策(金融緩和)に抵抗しました。
アベノミクス(金融緩和によるデフレ脱却)では財務官出身の黒田東彦を日銀総裁に任命し金融緩和を迫りました。
No.5 ユーロ圏をあやつる「第四帝国」
統一通貨のメリットとデメリットとは?
ユーロは欧州中央銀行(ECB)が発行しています。
第二次世界大戦後、米・ソの二極支配に対抗して欧州共同体(EC)が結成されました。
市場統合が実現すると、両替手数料と為替リスクをなくす目的で通貨を統合しました。
特に輸出大国の西ドイツはマルク高不況を避けられるため通貨統合をリードしました。
冷戦が終結し欧州連合(EU)が発足しました。
ユーロとECBは最大出資者のドイツ連邦銀行を中心に設立され、本部もドイツのフランクフルトに置かれました。
以降、金融政策はECBが決定し、各国中央銀行は通貨発行権も金利決定権も失いました。
中央銀行の独立を極限まで進めたと言えます。
ギリシア財政危機ではユーロ安になりドイツは収益を拡大しました。
ギリシア混乱→ユーロ下落→ドイツ輸出産業ぼろ儲け→ギリシアがECBにユーロ融資を求める→ドイツを中心とするECBがギリシアに内政干渉まがいの改革要求
軍事力で欧州を支配したナチスドイツ(第三帝国)に続き、今のドイツは「ユーロで欧州を支配する第四帝国だ」と皮肉られています。
イギリスはECBによる金融政策への干渉を嫌い、ポンドを守っています。
第2章 お金(2) 世界経済と国際通貨
No.6 なぜ、世界中の国々でドルが使えるのか?
金本位制と国際通貨について
大航海時代、アメリカ銀と日本銀が世界に流通し各国で銀本位制を確立されました。
当時、世界の覇権を握っていたスペインの銀貨(スペイン領メキシコで発行されたメキシコドル)は国際通貨として世界中に広まりました。
銀の価値の下落とともに19世紀に金本位制に転換します。
産業革命に成功したイギリスは、貿易で金を蓄え19世紀初頭にポンド金貨を発行しました。
ロンドンのシティは国際金融センターとなり、ポンドは19世紀を通じて国際通貨になりました。
背景には、当時のイギリスの圧倒的な経済力と海軍力があります。
しかし、第一次世界大戦でポンド→ドルの主役交代が起きました(No.8参照)。
No.7 明治日本が独立を維持できたのは、金本位制に移行できたから
明治の指導者たちの勇敢な決断とは?
江戸幕府はキリスト教と日本銀流出を恐れて鎖国しました。
鎖国前の金・銀交換比率を維持していた日本は、鎖国後に金が流出しました。
小判の金の含有量を下げ、貨幣の信用が低下しインフレとなりました。
明治政府は銀本位制を採用してインフレを収束させました。
世界の主要国は金本位制に移行しつつありました。
金本位制の採用には、政府(中央銀行)の大量の地金保有が条件です。
日本は日清戦争に勝利して得た銀を金に交換して金本位制に移行しました。
金本位制の採用で世界市場と結ばれた日本は、工業製品の輸出で稼いだ外貨を軍事費に投じて日露戦争にかろうじて勝利し、列強の一員の地位を確保しました。
No.8 ドルが強くなったのは、世界大戦のおかげ
アメリカはいかにして世界の覇者となったか?
第一次世界大戦では、欧州各国は金の流出を防ぐため金本位制から離脱し、不換紙幣を乱発し軍事費に充てました。
中立を宣言していたアメリカは軍需物資を輸出しました。
国際金融の中心がシティからウォール街へと移りました。
連合国の戦時国債を引き受けたアメリカは世界最大の債権国となり、米ドルが国際通貨になりました。
ロシア革命により連合国の勝利が揺らぐと、アメリカは債権を守るために参戦しました。表向きの口実はドイツによる無差別潜水艦作戦でした。
第二次世界大戦でもアメリカは連合国への武器輸出で世界恐慌から立ち直りました。
そして真珠湾攻撃をきっかけに参戦、勝利しました。
ヨーロッパと日本は焼け野原の一方、アメリカは無傷でした。超大国アメリカの出現です。
No.9 敗戦国日本は、なぜ経済成長できたのか?
ブレトン=ウッズ体制と貿易ルールの制定
第二次世界大戦に勝利したアメリカは以下のように考えました。
世界恐慌で各国が金本位制から離脱し、貿易が停止し日本とドイツが暴走した。
戦後は貿易を自由化しよう。関税を引き下げ、金本位制に戻そう。
ブレトン・ウッズ体制で1ドル360円に固定し、為替リスクをなくして貿易を促進させようとしました。
日本は戦後財政破綻し円の価値は暴落、インフレが起こり新円への切り替えを行いました。
そしてレートを固定することで、経済大国アメリカが円の信用を担保してくれたのです。
1960年代の日本経済の奇跡の復興後も円安が維持され、日本企業の輸出は促進されました。
No.10 国際通貨基金(IMF)と世界銀行はどう違うのか?
IMF=通貨の安定 IBRD=戦災復興
国際通貨基金(IMF)は、国際収支が極端に悪化した国へ米ドルの緊急融資を行います。
アジア通貨危機で韓国のウォンが暴落した際には、IMFが介入し韓国支援の条件として増税と公務員削減、財閥解体を命じました。
一方、世界銀行(IBRD)は、戦災復興と発展途上国支援をします。
日本は1953年以降、東海道新幹線、首都高速道路、黒部第4ダムなどの建設に総額8.6億ドルの融資を受けました。1960年に完済しました。
IMFもIBRDもワシントンDCに本部があり最大の出資者はアメリカです。よって親米政権への融資はすぐに認められます。
エジプトで親ソ政権が誕生した際にIBRDはアスワンハイダムへの融資を停止し、エジプトがスエズ運河国有化を宣言したことでスエズ戦争に発展しました。
No.11 円高・円安は、アメリカのルール違反から生まれた
固定相場制から変動相場制への移行
経済復興後も日本円と西ドイツマルクは安いレートで固定されていたため、両国の製品はアメリカに大量に輸出されました。
ニクソン大統領は金とドルの交換を停止しました(ニクソンショック)。さらに輸入品に一律10%の輸入課徴金を課しました。
ニクソンショック後のドル売りで固定相場制を維持できなくなり、変動相場制へ移行しました。
アメリカの威信は地に落ちた一方で、アメリカ製品が売れるようになりました。「名を捨てて実をとった」のです。
※ニクソン(アメリカ大統領)
泥沼化したベトナム戦争を収束するため、電撃的な訪中を行って毛沢東と会談し、和平を実現。
貿易赤字による金の流出を防ぐため、金とドルの交換を停止。
No.12 狂乱の時代ー日本のバブルはなぜ起こった?
プラザ合意による円高がすべての原因
1980年代は冷戦の最終段階でした。
アメリカは軍拡により財政赤字が拡大し、インフレ抑制のために金利を引き上げドル高となり、日本の輸出が拡大しました。
双子の赤字に苦しんだレーガン政権は円高ドル安の方向に協調介入させました。(プラザ合意)
日本は不利益を被ることを知りながら、対米関係の悪化は日本の安全保障に直結するため拒否できませんでした。
※レーガン(アメリカ大統領)
強いアメリカを唱えてソ連に軍事的圧力をかけ、冷戦終結への道を開く。
対日貿易赤字削減のため、円買いドル売りのプラザ合意を主要国に受け入れさせた。
そして円高不況へ突入しました。内需拡大のために金利を下げた結果、銀行預金が株式や土地に投資され、バブル経済が始まりました。
バブル経済は世界に飛び火し、NYのロックフェラーセンターまで日本企業に買収されました。
アジア諸国もバブルになり、アジア通貨危機をもたらしました。
No.13 タイ、インドネシア、韓国。3国はなぜ破綻に向かったのか?
アジア通貨危機の真相
ニクソンショック後も発展途上国は固定相場制を継続していました。
ニクソンショックとプラザ合意でドル安が急速に進展したことは、ドル・ペッグ制採用諸国の輸出産業に追い風となりました(特にアジアNIEs)。
しかし1990年代クリントン政権はドル高政策に転じました。3年間で1ドル79円から147円にドルが急騰しました。
合わせて韓国のウォンやタイのバーツも急騰し、ウォン高不況、バーツ高不況が起こりました。
変動相場制では、貿易収支が悪化すれば通貨が下落し国際競争力を回復しますが、アジア諸国はドル・ペッグ制から方向転換できませんでした。
※クリントン(アメリカ大統領)
ゴールドマン・サックス社のルービン会長を財務長官に迎え投資拡大のドル高政策に転換。
固定相場制のアジア諸国も通貨高となり、アジア通貨危機を招く。
国際金融資本ヘッジファンドはドルペッグ制崩壊前にアジア諸国の通貨を売り、暴落後に買い占めようとしました。ドルペッグ制を守ろうとタイはバーツ買いを支えましたが、バーツの暴落は続き変動相場制へ移行しました。同時に株価も地価も暴落しました。
インドネシアのルピア、韓国ウォンも暴落し、ドルペッグ制を維持できたのは香港ドルのみでした。
危機のあと通貨スワップが実現しました。日本銀行がアジア諸国の通貨の保証人になったのです。
No.14 「円」大暴落の危機!ヘッジファンドの正体とは?
利害の一致により、ヘッジファンドを撃退するが⋯
ヘッジファンドは、空売りで一気に売却し暴落させてから市場で再び買い戻すという手法で儲けます。
ジョージ・ソロスが率いるヘッジファンドはポンド売りでポンド危機を引き起こしました。
※ジョージ・ソロス(アメリカ、投資家)
ハンガリー出身のユダヤ系。
英のポンドを暴落させて「イングランド銀行を潰した男」といわれた。
東欧・旧ソ連地域の民主化運動を資金援助している。
ヘッジファンドは円に対しても、イラク戦争による円高の際に円を買い占め値段を吊り上げ、売り逃げようとしました。日銀は30兆円以上使って円を守り抜きました。
当時の小泉・ブッシュの蜜月関係も背景にあり、円を売って得たドルで米国債を買うことを約束したことでアメリカ財務省のテイラー財務次官からの協力も取り付けました。
アメリカは米国債を売った資金で軍事費を調達しました。
さらに公共投資を行い、余剰資金は不動産バブルを引き起こしました。サブプライムローンが販売され、不良債権となり金融機関を圧迫しました。
世界金融危機(2007)が引き起こされ、ドル・ユーロが暴落、日本は円高不況に苦しみ、民主党鳩山政権の成立(2009)につながります。

余談ですが、「ダム・マネー ウォール街を狙え!」は個人投資家とヘッジファンドの攻防を描いた映画で、とても面白いです!
No.15 ユーロ危機に見る「統一通貨の限界」
財政赤字国がユーロの足を引っ張る
ユーロの導入の際にはEUが財政状況を審査します。
ギリシアは基準を満たしていたはずが粉飾だったことが発覚しました(ギリシア財政危機)。

ギリシアについて、筆者の毒舌を抜粋します笑
プラトンやアリストテレスは、(中略)経済学については何も語っていません。中世(中略)、近代には(中略)専制官僚国家の支配を受け、勤労を美徳とする市民階級は生まれませんでした。19世紀に(中略)イギリスのおかげで独立。第二次世界大戦後は、(中略)アメリカが支援。常に「おんぶにだっこ」だった国がギリシアです。(中略)肥大した官僚機構。(中略)ばらまき福祉を続ける左派政権。(中略)脱税のための所得隠しが常態化している国民。
PIIGS諸国の巨額の財政赤字が明らかになりました。
ユーロ安が進み、PIIGS諸国は工業製品やエネルギーを輸入に頼る貿易赤字国であり苦しみ、逆に工業国ドイツは輸出を拡大しました。
経済力の違いすぎる国々が通貨統合したことに無理があったのです。
前編まとめ
以上が、茂木誠先生の著書「経済は世界史から学べ!」(2013, ダイアモンド社)の要約前編となります。
前編では、第1章、第2章の「お金」について要約してきました。
第3章以降もお楽しみいただけますと幸いです。
本書が気になった方はぜひ読んでみてください!
\ 他にも様々な分野の本を要約しています /