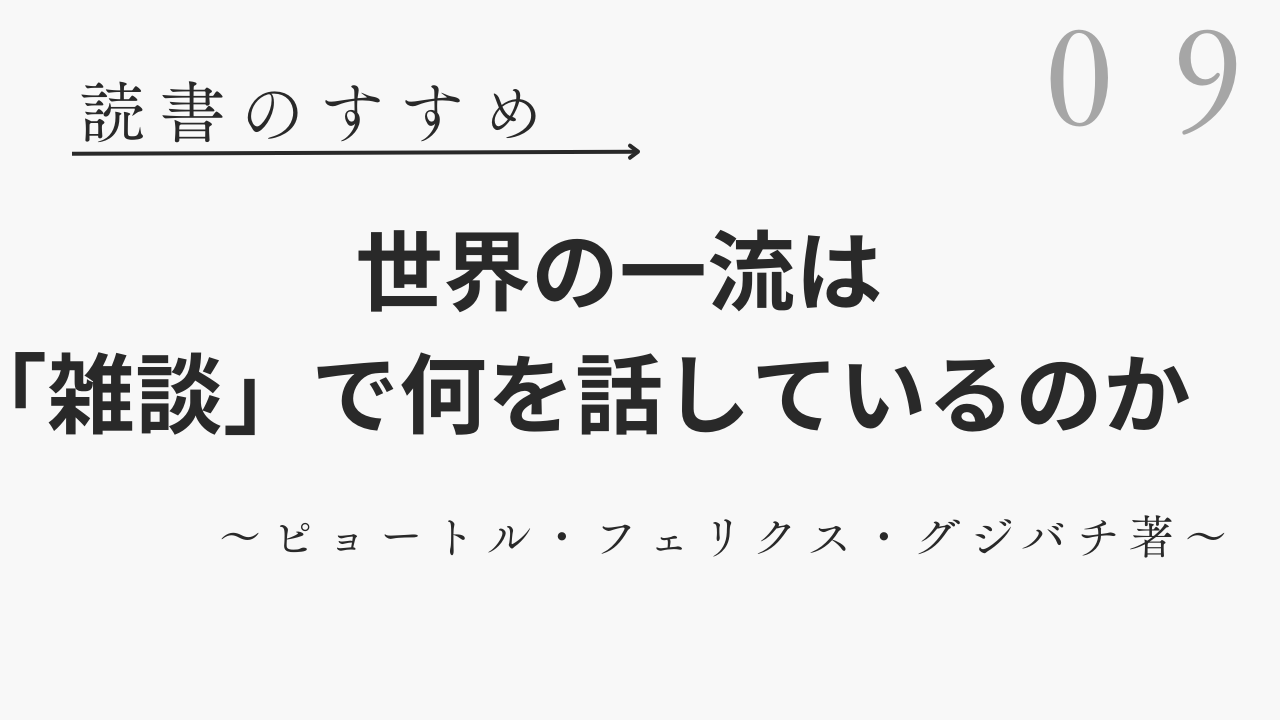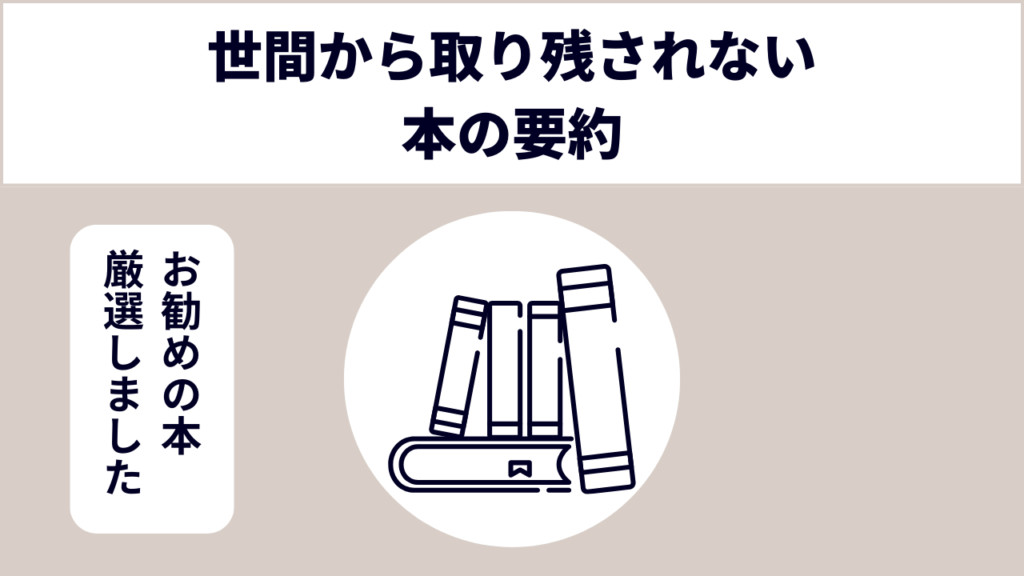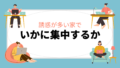今回は、ピョートル・フェリクス・グジバチ氏の著書「世界の一流は「雑談」で何を話しているのか」(2023年、クロスメディア・パブリッシング)の要約をしていきます。
ピョートル・フェリクス・グジバチ氏
・ポーランド出身
・連続起業家、投資家、経営コンサルタント、執筆者
・モルガン・スタンレーを経て、Googleで人材開発、組織改革、リーダーシップマネジメントに従事。
・2015年に独立し、未来創造企業のプロノイア・グループを設立。2016年にHRテクノロジー企業モティファイを共同創立し、2020年にエグジット。2019年に起業家教育事業のTimeLeapを共同創立。
まず序章で、日本人は「雑談」を世間話や無駄話と考えていますが、世界のビジネスマンはそうは捉えていない、という話から始まります。
それでは、世界の「雑談」と日本の「雑談」はどのように異なるのでしょうか。
第1章 ここが違う!「世界」の雑談と「日本」の雑談
一流の雑談には目的がある
日本人の雑談は、社交辞令、演技、決まり文句で構成され、定番のフレーズが多い一方で、世界の一流は相手に特化した雑談をし自己開示をすることでお互いの心理的距離を縮めています。
欧米は「社交的な会話」ができることが美徳ですが、日本では重視されておらず自分の頭で考え意見を持ち表現することに慣れていません。
良くも悪くも「自分が何をしたいのか?」「どうなりたいのか?」を考えなくても社会人として働けるのです。
しかし、多種多様な価値観を持つ人たちと良好な人間関係を構築するためには雑談を通して自己開示していくことが大切です。
自己開示の前段階として「自己認識」する必要があります。
- 「価値観」 何を大切にしているか
- 「信念」 何が正しいと思っているのか
- 「希望・期待」 何を求めているのか
この3つについて見つめ直して自己認識をし、自己認識➔自己開示➔自己表現➔自己実現というステップを踏むことが大切です。
日本のビジネスマンは、雑談を本題前のイントロと考え、利害関係の中で無難な話題を口にします。
一方で世界の第一線で活躍するビジネスマンは雑談を通じて次の3つを手に入れたいと考えています。
- お互いに「信頼」できる関係を築く
- お互いが「信用」できることを確認する
- お互いを「尊敬」できる関係を作る
雑談を通して、心理学で言う「ラポール」を作ることを目指しています。
ラポールとは、お互いの心が通じ合い、穏やかな気持ちで、リラックスして相手のことばを受け入れられる関係性です。
ラポールを得るには、目の前の相手に対して「無条件の肯定的関心」を持つことが大切です。
相手の感情に合わせ、相手の隠れた意図を読み取ります。
日本は民族の多様性が小さく、価値観が似通っている「ハイコンテクスト社会」です。そのため、自分の好みを伝えることは必ずしも美徳ではありません。
これに対して欧米は、人種や文化、価値観がそれぞれ異なるため、言葉でストレートに情報交換する必要があります。
一流の雑談には準備が必要
相手が意思決定するには、「この人でいこう」「この人たちに任せたい」と思わせるような心の動きを作る必要があります。
当社のことを調べ上げ、考え抜かれた面白いプランを持ち、他社と違う視点があり本質をわかっている、ということを伝える必要があるのです。
ビジネスの雑談は「B to B」ではなく「C to C」です。
欧米の一流のビジネスマンは周到な「準備」をして雑談に臨んでいます。
- 相手が求める情報は?
- 相手が知りたいことは?
- 相手の心配や不安なことは?
- 相手が納得するプレゼンのプロセスは?
- 相手の意思決定のタイミングは?
- 最終決定は誰がするのか?
一流が雑談に求めているのは「リベラルアーツ」です。地理や歴史といった教養も重視されます。
世界で活躍するビジネスマンは「グローバル」な視点と「トランスナショナル」な考え方を大切にして、文化や価値観の違いを乗り越えて信頼関係を築きビジネスで成果を出そうとしています。
そのため世界のビジネスマンは、会議のアジェンダだけでなく参加者個々のデータを収集して会議に臨みます。
- 会議の参加者はどんなメンバーなのか?
- それぞれの意見や見方は?
- 会議で聞きたいことは?
- 肯定材料、否定材料は何か?
さらに、相手の表情やその日の様子を確認することも大切です。
相手が不安を抱えている状況で準備した雑談をしても刺さりません。相手の心情を無視してビジネスの話に踏み込まず、「C to C」として向き合うようにします。
海外と日本では、ビジネスの相手との付き合いにも違いがあります。
欧米は最初にビジネスがありその後に付き合いが始まる「トランザクション」の文化です。
日本はビジネスが成立する前に関係を深める「リレーション」の文化です。
第2章 グーグルの強さの秘密を知る!強いチームをつくる「社内雑談力」の極意
日本企業の「社内コミュニケーション」は転換期を迎えています。
- 「ダイバーシティ&インクルージョン」という問題:性別や年齢、国籍、文化、価値観など多様な背景を持つ人材を幅広く活用することで新たな価値を創造
- 出口が見えない「働き方改革」の問題:労働時間短縮だけでは解決できない課題
- パワハラ&セクハラ意識の高まり
日本では、上司の指示や意見は「絶対」と考えられていましたが、現在では誰の判断が正しいのかわからないような時代になりました。
一方で黙ってルールに従いなさいという企業も未だに多いのが実情です。
Part1 グーグルは雑談とどう向き合っているか?
◆社員が自分の意見を経営陣にぶつける機会がある:TGIFという経営幹部に直接質問できるミーティング
◆意図的に雑談の機会を作るオフィス設計:狭い通路を通る設計、一人席のない食堂
◆2000人以上の部下の名前を覚えた人事トップ:名前を呼んでから雑談をすることの重要性
◆マネジャーとメンバーは上司と部下の関係ではない:スポーツチームのコーチと選手のような関係
◆誰とでも気軽に「1 on 1」ミーティングができる文化:日常的にお互いの情報をアップデート
◆グーグルの躍進を支える原動力は「風通し」の良さ:自由な雰囲気

余談ですが、アメリカで某音楽配信サービス会社の見学をしたことがあり、とても開放的な雰囲気で驚きました。
この本を読んだ後に見学していたら尚更楽しかっただろうなとも思います…^^;
Part2 なぜ「社内の雑談」が重要なのか?
◆「雑談をするチームは生産性が高い」というエビデンスがある
◆職場の雑談には7つの「相乗効果」がある
- 職場の人たちと仕事以外の「つながり」ができる
- お互いの「信頼感」が高まる
- 職場の「心理的安全性」が高まる
- 「働きやすい環境」が生まれる
- 仕事の「モチベーション」が高まる
- ミーティングで「発言」しやすくなる
- 会議の「結論」に納得して働けるようになる
◆雑談の不在は人間関係の悪化を招きやすい:雑談を通じて、メンバーの仕事以外の外的要因も視野に
◆笑い声が聞こえない会社には何らかの問題がある:仕事で成果が出ているから笑うことができ、笑いを許容できる
◆雑談によって周囲の「バイアス」を低減する:人間関係の悪化も招くバイアスを雑談を通じて排除
◆働く女性が新たに直面している「慈悲的性差別」の回避:一見すると善意や親切心のような性差別
Part3 マネジャー(上司)に求められる雑談とは?
◆部下の状況を確認しながら、成果につながる会話をする
◆サポートができなければ、話に耳を傾けるだけでもいい
◆「1 on 1」ミーティングは雑談だけで事足りる:何度も話を聞いてようやく本音にたどり着ける
◆「キャリア・カンバーせーション」も雑談で対応できる:雑談の折に軽くテーマを振って次までに考えさせる
◆明確な目的を持って、日常的に雑談する習慣を作る
◆マネジャーはもっと自分の「弱み」を開示していい:常に謙虚な姿勢を貫ける人間的強さ
◆若手マネジャーも下の世代に悩んでいる:テクノロジーを巧みに使いこなす20代を財産とみなして活用
◆「マイクロマネジメント」よりも雑談を心がける:過干渉せずにチームの方向性を示したうえで、メンバーの自主性を尊重してモチベーションを高める
Part4 メンバー(部下)に必要な雑談とは?
日本企業の管理職は大半が「プレイング・マネージャー」です。
日本のマネジャーはマネジメントの専門的知識を持たず自分の経験値だけを頼りにマネジメントしています。
雑談を通じて上司から以下の情報を得ることが大切です。
◆上司の立ち位置の確認
- どんな考えを持って、仕事と向き合っているか?
- 仕事に求めることは?(出世、給料、自分の時間)
- 自分自身の仕事内容の評価は?
- 自分の上司との関係は?
- 自分の上司から求められていることは?
◆部下に対する評価の基準
- 部下を評価基準は?
- それぞれの部下の評価は?
- その評価を自分の上司にどう説明するのか?
- 部下がどんな成果を上げることを期待しているのか?
- 理想の状況は?
- 部下に求める働き方は?
◆リスク管理に関する視点
- 困っていることは?
- リスクと考えていることは?
- 長期的にどうしていきたいのか?
部下が上司に仕事を教えたり場合によっては反論するという、「マネジャーをマネジメントする」視点もこれからの時代には大切です。
またマネジャーを安心させるために、「オーバーコミュニケーション」を意識し、過不足なく、あるいは必要以上に細かく情報を発信しましょう。
さらに上司は何を求めていることは何かを考え、それを検証するような雑談を日頃から積み重ねます。
第3章 どうすれば結果が出せるのか?武器としてのビジネスの雑談
雑談の最初のミッションは「確認作業」をすることです。
「相手の状況」、「ビジネス状況」、「新たに必要となる情報」を確認します。
さらに雑談で相手企業の「意思決定」の流れを確認します。
ビジネスの雑談を通じて「ライフタイムバリュー」を高めることで、長期的な成果を上げられる関係を築きくようにします。
ビジネスの雑談には4つの「目的」があります。
- 「つながる」 相手との距離を縮めて信用を作る
- 「調べる」 最新の動向や現状に関する情報を収集する
- 「伝える」 自社の意向や進捗状況などを報告する
- 「共有する」 最新の情報を相互に認識する
日本のビジネスマンは相手と「上下関係」を作ってしまいがちですが、成果を出す営業マンは対等な人間関係を作ります。
ビジネス相手と「対等」な関係を作るためのアプローチには、お互いの共通の趣味を見つけたり、お互いに共通する体験や考え方を共有したり、相手にとって必要不可欠な存在になったり、ということがあります。
興味と好奇心を持って相手に意識を集中することで、相手もこちらに興味を持つようになります。
ラポールを作るには、①相手が何を大切にしているかを知る、②相手が何を正しいと思っているかを知る、③相手が何を求めているかを知る、という3原則があります。
3原則を知るためには以下の7つの質問が有効です。
- 仕事を通じて何を得たいか
- それはなぜ必要か
- 何をもっていい仕事をしたと言えるか
- なぜ今の仕事を選んだのか
- 去年と今年の仕事はどのようにつながっているか
- 一番の強みは何か
- 今どんなサポートが必要か
異業種の相手には「サイクル➔トレンド➔パターン」を聞き、業界のサイクルとその中で最も新しいトレンド、顕著なビジネスモデルのパターンを質問します。
エグゼクティブは雑談で、相手にお金で買えない価値があるかという「スクリーニング」をしています。
筆者は以下のリストでエグゼクティブを質問攻めにしているそうです。
- ビジネスを始めたきっかけ
- 過去の挫折体験
- ブレイクスルー体験
- 現在のミッション
- ビジネスに関する価値観
- ビジネスに向き合う際の信念
教養を身につけるには時間がかかりますが「質問力」は短時間で身につきます。
相手が答えやすい状況を考えて意図的に情報を集め、情報収集のための明確なイメージを持つことでチャンスをものにできます。
雑談を武器として活用するためには、①雑談を1回限りのチャンスと考える必要はない、②知り得た情報をどう活かすかという視点を持つ、③前回の内容をしっかりと覚えておく、という心構えでいましょう。
第4章 何を話すべきではないのか?こんな雑談は危ない!6つのNGポイント
何を聞かない方がいいことも合理的に判断する必要があります。
- 相手のプライベートに、いきなり踏み込まない:質問のアングルを変えて質問を重ねる
- 「ファクト」ベースの質問は意外に危険:価値観ベース、信念ベース、期待ベースにする
- ビジネスの場で「収入」の話はしない
- 「シチュエーション」を考えた雑談を心がける
- 「宗教」の話は無理に避ける必要はない
- 「下ネタ」で距離感が縮まることはない
ラポールがすでにできているなら、あえて「雑談をしない」という選択肢もあります。
まとめ
以上が、「世界の一流は「雑談」で何を話しているのか」の要約となります。
私は、いわゆるビジネスマンではないのですが、上司との関わり方など参考になる点が多くありました。
割愛した箇所もたくさんありますので、ぜひ原著を手にとっていただければ幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました(^^)
\ 他にも様々な分野の本を要約しています /